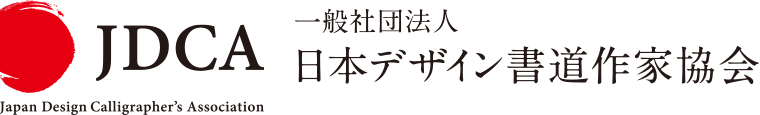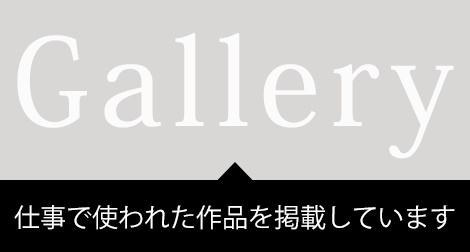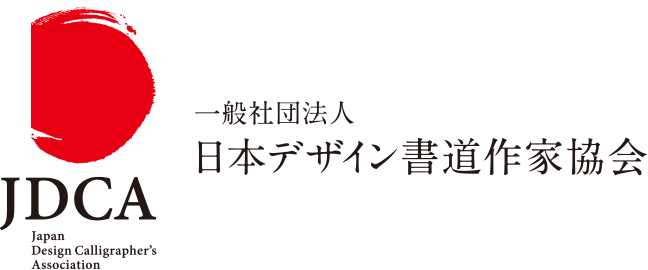漢字書体の歴史
今回のワークショップでは、拓本を通して「書体」「書風」「字体」「字形」を検証し、文字の歴史から、現代へ通じるデザインへの結びつきを探ることが狙い。岡本氏による臨書を通して、その筆遣いを存分に学んだ。
筆文字を作成するにあたって、まずどんな書体を選択し、字形はどうするか、そしてどのような書風で仕上げるのか。そもそも書体はいつからできたのか。。。篆書・古隷・隷書・草書はお互いに文字構造に影響を与え合いながら筆法を確立させ、文字は広く人々に行き渡り、様々に文字が使用され工夫されるようになる。
そして三国時代以後の楷書・行書の成立と書聖王羲之の登場となる。
書風の特長
配布された拓本のコピーは、漢字五書体をはじめ、魏碑体と呼ばれる造像記、木簡に記された筆法。書体や字形、書風から感じられるものは書法によって表現されている。
書法の三大要素

「筆法(ひっぽう)」(筆の持ち方や線の引き方)
「間架結構法(かんかけっこうほう)」(構図の決め方やレイアウト)
「布置章法(ふちしょうほう)」(空間の取り方やトリミング)
私たちが文字をデザインするにあたり、ついパターン化しがちにならないためにも、こうした先人たちが残した名跡から学ぶことができる。